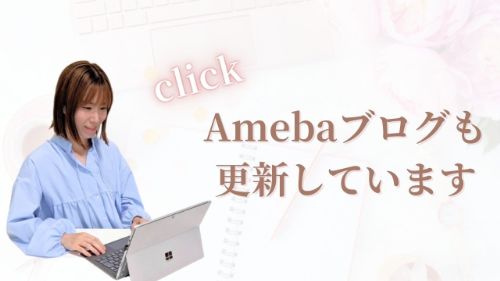「1番」になれなくても、意味がある。〜ピアノの習い事で育つ“折れない心”〜
八王子市Sakiピアノ教室、飯沢です。
「1番を取った!」
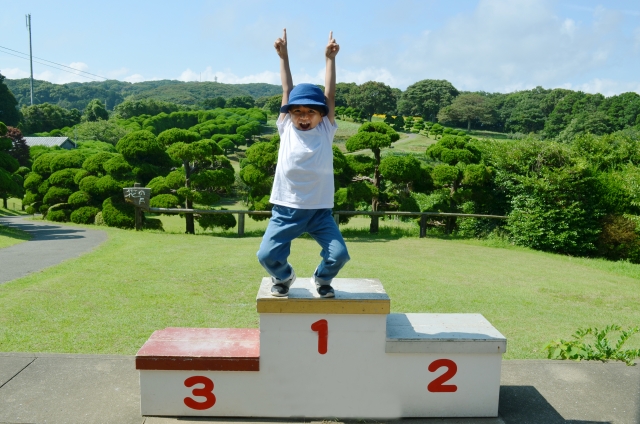
そんなキラキラした経験を、お子さんにさせてあげたい。
親なら誰しも、そう思うものです。
実際、習い始めの頃は少しの努力でも目立てたり、周りに褒められたり、学年で一番、クラスで一番…そんな“成功体験”が手に入るかもしれません。
でも、やがて出会います。
「自分より上の子」。
同じ学年の別の子かもしれない。
外部のコンクールかもしれない。
全国レベルの動画を見て、衝撃を受けることもあるでしょう。
そのとき、子どもはどうするか。
心が折れる子もいます。
「もうやりたくない」「どうせ無理…」と口にするかもしれません。
でも、ピアノの習い事が「本当の意味での力」を育ててくれるなら。
それは、そんな“挫折”を超えて、また立ち上がる力ではないでしょうか?
小さな世界で“1番”になることの価値
まず、身近な中で努力して成果を出す経験は、子どもにとって非常に大切です。
「やればできた」という自信は、その後の挑戦の土台になります。
ピアノの発表会、学校での合唱伴奏…
これらはすべて「自分の力でつかんだ1番」であり、宝物です。
でも、ずっとその中だけで過ごしていると、「努力すれば必ず1番になれる」と勘違いしてしまうことも。
だからこそ、少しずつ世界を広げてあげる必要があるのです。
上には上がいる。その現実を知ったとき
大きな大会やコンクール、今ではYouTube動画で見た天才たち。
子どもは衝撃を受けます。
「なんでこんなに弾けるの?自分がんばってるのに…」
「もう無理。自分には才能ない」

ここで、ある子は諦めます。
でもある子は、「よし、もっとがんばろう」と思える。
この差はなんでしょうか?
「がんばった自分」を認める力
一度の挫折でやめてしまう子は、「結果」だけを見ています。
でも、そこに至るまでの「プロセス」を自分で見つめられる子は、強い。
私の教室では、演奏の“出来不出来”よりも、「前よりできた」こと、「取り組んだ時間」、「工夫した方法」をしっかり見つけ、伝えるようにしています。
「1番じゃなくても、前の自分より進んでる」
そう思える子は、どんな世界でも歩き続けられます。
先生や家族ができるサポート
子どもが心を折られそうになったとき、大人の関わり方はとても重要です。
- 悔しさに共感する(「悔しかったね」「びっくりしたよね」)
- 過程を認める(「毎日練習したこと、先生見てたよ」)
- 「負けたから終わり」ではなく、「ここからどうするか」を一緒に考える
大切なのは、「結果で価値が決まる子」にしないこと。
「成長しようとする姿勢」にこそ価値を置いてほしいのです。
ピアノだからこそ学べる“乗り越える力”
ピアノはすぐに結果が出ない習い事。
だからこそ、積み重ねた人だけが見える景色があります。
「昨日できなかったことが、今日できた」
「難しかった曲が、少しずつ指に馴染んでくる」
そんな経験を通して、子どもたちは「自分には進む力がある」と実感していきます。
そして、きっと気づくのです。
「上には上がいても、比べるべきは“昨日の自分”だ」と。
結果より“歩き続ける力”を育てたい
ピアノを習うことは、音楽の技術を磨くこと以上に、
「途中で投げ出さずに、自分と向き合い、乗り越えていく」
そんな“人としての力”を育む場でもあります。
これからの社会で必要とされるのは、すぐに結果が出なくても学び続けられる子、自分なりのゴールに向かって歩き続けられる子です。
だからこそ、私たち大人が見たいのは「1番になったとき」ではなく「立ち上がったその瞬間」なのかもしれません。
ピアノを通して、そんな一歩を一緒に育てていけたら嬉しいです。