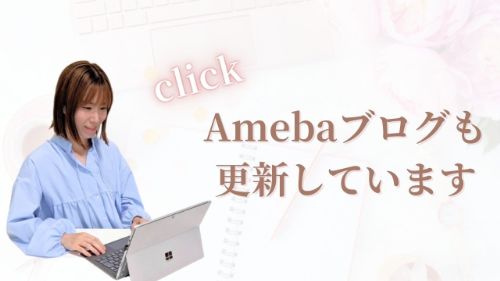「感じる心」と「基本の力」。ピアノの学びの本質とは?
八王子市Sakiピアノ教室、飯沢です。
ピアノのレッスンでは「感性を育てる」「表現力を伸ばす」といったイメージを持たれる方が多いかもしれません。
もちろんそれはとても大切なこと。
でも、もう一つ忘れてはいけないのが“基本を学ぶ”ことの大切さです。
音楽は自由な表現の世界ですが、自由に表現するためには、まず“土台”が必要。
その土台となるのが、
「楽譜を読む力」
「音の聴き方」
「体の使い方」
などの基本です。
基本を学ぶことは「感じる力」を育てること
「基本=堅苦しい練習」という印象を持たれる方もいるかもしれません。
ですが、実は基本を学ぶことでこそ、感じる力が磨かれていきます。
たとえば、同じ音でも、姿勢・指の形・タッチの速さで全く違う響きになります。
その違いを耳で聴き分けられるようになると、自然に“音を感じる感性”が育ちます。
また、正しい姿勢で弾くことは、呼吸のように自然な演奏へとつながります。
体の使い方が無理のない状態だと、音が伸びやかに響き、自分の音をより深く味わえるようになるのです。
つまり、基本を身につけることは、「表現の幅を広げる」ための第一歩なのです。

楽譜の中にはたくさんの“ヒント”がある
楽譜は、ただ音の高さや長さが書かれた紙ではありません。
そこには、作曲家が伝えたい物語や感情が隠されています。
強弱記号、スラー、アクセント、テンポの指示……
書かれてある記号一つひとつに意味があり、それを読み取ることで、音楽がぐっと立体的に見えてきます。
最初のうちは「読むこと」に精一杯かもしれませんが、少しずつ「見える情報を音に変える力」がついてくると、子どもたちは自然に音楽の世界を“感じ取る”ようになります。
「楽譜が読める」ことは、“感じた心を形にできる力”でもあるのです。
応用は「基本」の積み重ねの先にある
「もっと自由に弾けるようになってほしい」
「表現力をつけてあげたい」
そう願う保護者の方は多いと思います。
私も同じ気持ちです。
ピアノを習うすべての生徒が、自分で楽譜を読み、それを音として表現できる力がつくように…と思っています。
でも、自由な演奏は、“基本の積み重ね”の先にあるもの。
基本の型を身につけたうえで初めて、テンポを揺らしたり、音の強弱をコントロールしたりと、自分の意志で音楽を動かすことができるようになります。
これはまるで、言葉を覚えていく過程と似ています。
語彙(音)を増やし、文法(基礎)を学ぶからこそ、やがて自分の言葉(表現)で話せるようになる。
ピアノも同じで、基本があるからこそ、自分の「感じた音」を自由に奏でられるのです。
基本を大切にすることは、自由への第一歩
ピアノレッスンでは、「感じる心」と「基本の力」どちらも大切にしています。
基本をしっかり身につけることで、その先の音楽がもっと自由に、もっと豊かに広がっていきます。
“感じる心”を支えるのは、“整った基礎”です。
そして、その両方がそろったとき、子どもの中から自然に生まれる音は、まさに「自分の音」になります。
時にじれったく感じることもあるかと思いますが、子ども達を信じて今の力を認めてあげてください。