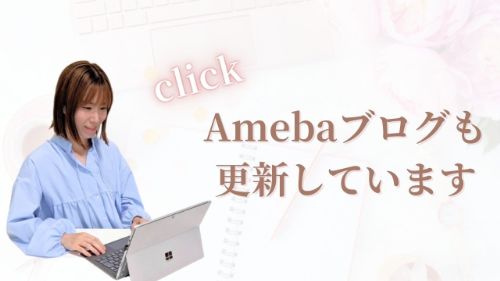「できる!」が育つ、【待つ】レッスン
八王子市Sakiピアノ教室、飯沢です。
2歳・3歳になると、「自分で!」という言葉が増えてきますね。
靴を履くのも、片づけをするのも、時間がかかるけれど「自分でやりたい」。
その気持ちは、まさに“成長のサイン”です。
でも、忙しい毎日の中ではつい…
「こぼれるからママがやるね」
「時間ないから、やってあげるね」
と、先回りしてしまうことも。
でも実はこの“手助けのタイミング”こそが、子どもの成長を左右します。
本人がやろうとしているときに、少しでも大人が手を出すと、子どもは
「自分ではできない」
「どうせやっても無理」
という“思い込み”を少しずつ積み重ねてしまいます。
その逆に、“信じて待ってもらえた経験”は、子どもの中に「自分でできた!」という自信を残します。
その積み重ねが「挑戦できる子」を育てていくのです。

今ちょうど次女が2歳。
まさに「○○ちゃんがやる!」
「できるもん!」
の時期で、時間がない時はついつい待ってあげられない時もあります。
日常では中々難しいこともあることは承知したうえで、私がレッスンで大切にしている考えをお伝えします。
これは、幼児だけではなく、全生徒に共通して意識しています。
“待つ”ことは“育てること”
レッスンの中でも、子どもが考えている時間はとても大切です。
たとえば、音符カードを見て少し黙り込む子。
その間、大人はついヒントを出したくなりますが、実はここが一番大切な時間です。
子どもはその沈黙の中で、
- 記憶をたどる
- 自分の中のルールを思い出す
- 答えを確かめる
という“思考の筋トレ”をしています。
もし先に答えを教えてしまうと、思考の筋肉は育たず、ただの「当てっこ遊び」になってしまいます。
だからこそ、少しの間でも“待つ”。
この“待つ時間”が、実は「できる力」をゆっくりと育てているのです。
レッスンでは“待ち方”にも工夫があります
とはいえ、ただ黙って見ているだけでは、子どもの集中は続きません。
教室では、次のような工夫をしています。
① 見守りの言葉を添える
「次はどうするんだったかな?」
「ここまでできてたね!」
と、安心感を与える声がけをすることで、子どもは自分のペースで再び考えることができます。
② 気持ちの切り替えをサポートする
教具を使ったり、実際に体を動かしたり、伝え方を大げさにしてみたり(笑)、視覚・触覚から集中を戻す工夫も取り入れています。
“待つ”とは、ただ時間を与えることではなく、子どもが再び自分で考えたくなる環境を整えることでもあるのです。
③ 「できた!」を共に味わう
できた瞬間には、しっかりと共感を返します。
「そう!」
「自分で見つけたね!」
「考えてたもんね、すごいね!」
この言葉が、次の挑戦へのエネルギーになります。
大人が“待つ力”を持つことで、子どもは伸びていく
大人が少しだけ勇気を出して“待つ”と、子どもはその信頼を感じ取ります。
「きっとできる」と思ってもらえた経験は、自己肯定感の土台になります。
逆に、「やってもらう」「助けてもらう」ことが当たり前になると、挑戦する前に諦める子になってしまいます。
小さな“待つ勇気”が、子どもの大きな“できる力”を引き出していく。
レッスンを通して、その瞬間を見守れることは、指導者として何よりの喜びです。
まとめ:子どもの「できる!」は、信じて待つ大人が育てる
ピアノレッスンでも、家庭の中でも、子どもが“できる!”と思える瞬間は、「誰かに信じてもらえた時間」から生まれます。
焦らず、比べず、手を出さず…
子どもが自分の力で考え、行動し、成功を味わう。
その一つひとつの体験が、未来の「やればできる!」をつくっていきます。
“待つ”という選択は、時間がかかるようでいて、実は最も確実な近道なのかもしれません。