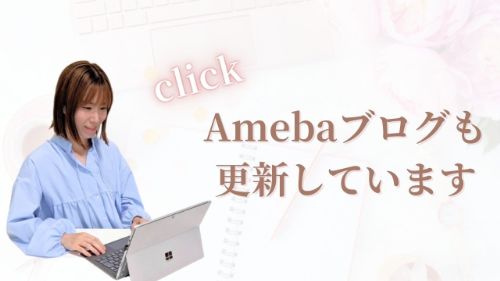音感レッスンがもたらす効果
Sakiピアノ教室、飯沢です。
今日は、当教室の
のレッスン内で行っている音感レッスンについて、内容と、その効果をお話しします。
音感とは、音と音での経験の一致がもたらすもの
ここで扱う「音感」とは「絶対音感」も含めたお話しをさせていただきます。
- ドレミが分かること
- 音の持つ色が分かること
- 音の持つ感情を読み取れること
これらをまとめて、「音感」と呼ばせていただきます😌
いわゆる、この「音感」とは、
音と音での経験が一致すること
だと思っています。

絶対音感の身につけ方とは?
絶対音感を例に挙げると、毎日和音を聞いて、トレーニングを行っていきます。
まずは和音と色を一致させるトレーニング。
「♪ドミソ~」→「あか!」
これを耳の黄金期に繰り返していくことで、最終的には単音ででも何の音か聞きとれる音感を身につけていきます。
毎日毎日、何をやっているかというと
音での経験を増やしていっているわけです。
例えば、物が落ちる音がしたら、その音の種類でどんな形状のものがどんな高さから、どのように落ちたか、想像できますよね。
それは、今までたくさんの音での経験を繰り返しているからです。
絶対音感は、ほんのわずかな音程の差も聞き取れるように、耳の黄金期に始めるべきだとされています。
毎日のトレーニングなしでも絶対音感が身についていた話
さて、
「耳の黄金期に毎日トレーニングを行わないと、絶対音感が身につかないのか…」
と思われた方もいらっしゃるかと思います。
ではここで、毎日のトレーニングなしでも絶対音感が身についていた話をさせていただきます。
我が娘の話なのですが…
ある日、長女が4歳になるくらいの頃。
ふと指がピアノにあたり、1つの音が鳴ったんです。
そしたら、ピアノの鍵盤が全く見えない場所にいた長女が急に
「なんでいま『ソ』って弾いたの?」
とたずねてきたのです。
確かになった音は『ソ』でした。

その後からも、おもちゃの音やスマホのアラームの音をあてるなど、長女はおそらく絶対音感が身についているんだろうなという出来事が日常で見受けられるようになりました。
では彼女が日々していたことはなんだったのでしょうか?
なぜ、知らず知らずのうちに絶対音感が身についていたのでしょうか?
音での経験がたくさんあった
彼女は、音での経験がたくさんありました。
生後まもなくから、抱っこされ、ピアノのレッスンに付き合っていたのもありますが…
長女は2歳のころからピアノレッスンをはじめています。
そのレッスン内では必ず、ドレミを歌いながら、ピアノを弾いていました。
そして日常でも、彼女はたくさんドレミで歌を歌っていました。
自然と行っていたこの経験が、彼女の中で
「この音の響きは『ド』なんだ」
という、絶対音感を身につける経験につながっていったのだと思います。
日々の経験を音と一致させていく
「この音はえんえん(泣いている)音がする」
「小鳥さんの鳴き声みたい」
「雷が落ちた音かな?」
こんな、音へ対するイメージは、子どもたちが得意とする分野です。

しかし、小学生くらいになると、あんなに純粋に音がきけていた子も、頭でいろいろなことを考えてしまい、心の中でストップをかけてしまいます。
そうなる前に、音での経験をたくさん増やし、それを表現できる場、すべてが正解!と言ってくれる場があれば、子どもたちは自身をもって音感を身につけることができます。
この音へのイメージも、すべて経験からくるものです。
大人がいくら
「小鳥さんの声だね」
「雷が落ちた音だよ」
といっても、子どもが実際にその音を聴かない限り、音での経験にはつながりません。
実体験があってこそ、身につく音感です。
毎日のトレーニングは難しくても音感は身につけられる
絶対音感を確実に身につけられるのは、毎日のトレーニングが必要な絶対音感トレーニングかもしれません。
しかし、
「そこまでするのは無理。ドレミがなんとなく聞き取れるだけでも、じゅうぶん音楽を楽しめるんじゃないかな?」
そう思われる方も多くいらっしゃると思います。
音を聴いて、それをピアノで弾けるようになると楽しいのは安易に想像がつきますよね。
(もちろん相応のテクニックも必要ですが)
絶対音感を身につけることで、IQが10~20高くなるともいわれています。
Sakiピアノ教室の
では、年間でたくさんの音と音での経験を増やしていきます。
音を聴いて体で表現したり、
なじみのある曲をドレミで歌を歌ったり、
いろんな音での経験で、音感をどんどん身につけてほしいと思っています。
聴く耳を育て、今後の長い人生においても音楽が役立つように、丁寧に丁寧に音感を育てていきます。
親子ではぐくむプレピアノ【つむぎコース】は
- 八王子市緑町教室
- 八王子市みつい台教室
- オンライン動画レッスン
を展開しています。
教えない!感覚で学べる特製教具、カリキュラムを使い、親子での音楽時間を楽しめるレッスンです。
お子さまの「今」に寄りそい、幼児期だからこそ育てられる力を引き出していきます。
お子さまに「楽しい!」からピアノの世界を見せてあげませんか?

八王子市Sakiピアノ教室では生後6カ月のベビー期より音感リトミックのレッスンを行っています。
- みつい台教室
- 動画レッスン
で全国各地よりご受講いただけます。
脳がとっても柔らかく、スポンジのように吸収していく乳幼児期に、音での経験を増やしませんか?
こちらのページより、レッスン詳細をご確認ください。