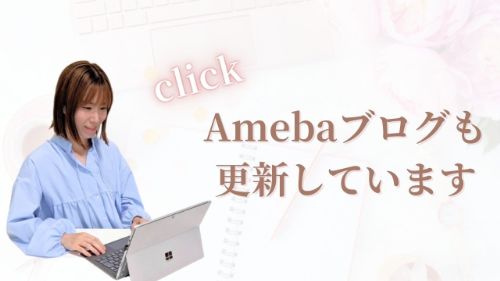子どもが最大限に集中力を発揮する?!私の作る教具がシンプルなワケ。
八王子市Sakiピアノ教室、飯沢です。
私が作る2歳からのピアノ教具。
手に取った方はお分かりいただけると思いますが…
余計な装飾やイラストは一切排除。
子どもに学んでもらいたい内容だけを詰め込んだ、そんな教具です。
それゆえ
「とっても使いやすいです」
「応用がきいて助かっています」
「生徒が集中して、お母さんもびっくりしていました!」
教具を手に取っていただいた先生方からは、そんな声を良く頂戴します。
過去は、教材に“かわいさ”や“ワクワク”を足せば、子どもは楽しんでくれるはず!
そう信じて、レッスンしてきていました。
でもあるとき、「それ、本当に“子どものため”になってる?」と自分に問い直す出来事がありました。
子どもは元々、集中が持続しにくい特性があります。
とくに2〜5歳の未就学児は、“視覚的な刺激”にすぐに注意が移ってしまいます。
つまり、教具がごちゃごちゃしていればしているほど、「今やるべきこと」に集中しづらくなるんです。
そこで私は思い切って、「装飾を削ぎ落とす」方向へシフトしました。
するとどうでしょう?
子どもたちの集中力に、明らかな変化が現れたのです。
今日はそんな私の取り組みについて、
「なぜ装飾を排除することで集中できるのか?」
「どんな子にも効果がある理由」
そして
「具体的にどういう教具が役に立つのか?」
を、保護者の方にも先生にもわかりやすくお話ししていきます。
なぜ子どもは集中しにくいのか?
未就学の子どもにとって、“集中力”とは鍛えるべき能力ではなく、「育つ環境が必要な種」のようなものです。
脳の前頭葉はまだ発達途中で、ひとつのことに意識を向け続けるのが難しい。
でも、逆に言えば、「何に意識を向けるべきか」が明確ならば、集中できる力は備わっているのです。
ここで問題になるのが“過剰な視覚刺激”。
文字、イラスト、色、キラキラ…。
これらがあると子どもの脳は“処理すべき情報”が多すぎて、本来の目的(音を聴く、リズムを感じる、指を動かすなど)にたどり着けなくなってしまいます。
見た目を削ぐことで「本質」に近づける
私はこれまでに、たくさんの教具を試作してきました。
そのなかで気づいたのは、「情報を減らすほど、子どもが“自分で意味を見出そうとする”」ということです。
たとえば、音列に合わせた色のついた鍵盤模様のカードと同じ配色のおはじきをそっと子どもに渡します。
それを見た子は「これはなに?」「どうするの?」と自然に先生の言葉を聞こうとします。
そして自分でいろんなことを考えます。
気が付いたときには、教具に込めた大切な学びに気が付き、集中していじっています。

つまり、教具が“主張しすぎない”ことで、子ども自身が“学ぼうとする姿勢”を取るのです。
教具デザインにおける3つのポイント
- ①「余白」を活かす
-
子どもの目と脳が“迷わない”ためのスペースをあえて作る。
- ②「1回=1情報」ルール
-
一度に伝える情報はひとつだけ。多くても2つまで。
- ③「注目すべき場所」だけを目立たせる
-
強調したいところだけに限定。
こうした工夫を取り入れるだけで、子どもは驚くほど集中してくれるようになりました。
とくに「見た瞬間に“何をすればいいか”がわかる」デザインは、レッスンのテンポアップにもつながります。
よくある誤解:「かわいい=子どもが喜ぶ」?
先生方と、やり取りをしていると「かわいい方が子どもは楽しかな?と思って…」といろいろと工夫している先生のお悩みに触れることもあります。
もちろん“楽しさ”は大事です。
でも、それが「目的から注意をそらすもの」であれば、逆効果になります。
大人でも、パワーポイントがごちゃごちゃしてる会議、装飾たっぷりな資料より、すっきり整理された資料の方が集中しやすいですよね。
子どもも同じ。
むしろ、大人よりもっと“整理された情報”を必要としているのです。
子どもの感覚を刺激する、シンプル設計の教具紹介
ここで、私が作っている教具から、「使いやすい!」と好評で、人気のものをご紹介します。
絵カードリズムセット
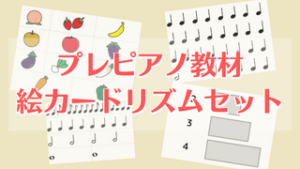
絵のリズムごとに、カードの大きさを変えています。
子どもが手に取った時に、パッと見て分かりやすく、教えなくても、子どもが自分から気がつく設計です。
幼児期はひらがなに興味を持つ時期なのもあり、発音ベースではなく、ひらがなベースでリズムを作っています。
例:ぶどう→タンタンタン(×タンたーあん)
また、この教具では、リズムの導入だけではなく、黒鍵の導入にも使え、鍵盤の配置、運指まで指導することが可能です。
鍵盤教具

こちらの教具は、色を使って鍵盤把握ができるように作ってあります。
同じ色を用いて、おはじきやピンチを一緒に使いながら活動を行います。
カラフルな教具ではありますが、無駄は一切なく、必要な情報のみ。
色のマッチングはもちろんのこと、色と音の一致、他の教具と合わせて使うことで、音符カードへの橋渡しとなる教具です。
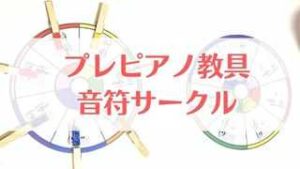
模様よみ
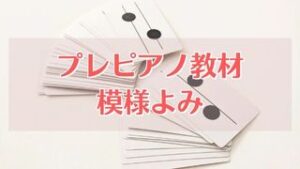
模様よみの教具も、一切の無駄なく作っています。
幼児期から楽譜に親しむためには、音符カードに加え、模様よみが必須。
▶実は…音符カードだけでは楽譜は読めない
まずは〇がどこにあるのか。
どのように動いているか。
一緒はどれ?
一緒は作れる?
段階を経て、〇(音符)の前後のつながりを意識できるようにしていきます。
必要な情報だけ見せる工夫を
子どもが集中できないのは、性格や能力のせいではありません。
子どもは本来、とても敏感で賢く、“感じとる力”を持っています。
だからこそ、必要以上の情報があると、頭も心も疲れてしまうのです。
私たち大人ができることは、子どもに合わせて情報を整理し、伝えたいことだけをシンプルに伝える環境を整えること。
教具は、そのための大切なパートナーです。
ピアノは、音と動きと感覚が複雑に絡み合う習いごと。
だからこそ、「どう見せるか」「どう感じさせるか」がレッスンの質を大きく左右します。
かわいさや賑やかさは一時的な興味を引くことはできても、集中し、学び、身につけるためには「引き算の美学」が必要です。
もし、お子さんが「なんだかレッスン中に落ち着かないな…」と感じている方がいれば、一度、教具や環境を“引き算の目”で見てみてください。
そして、同じように日々指導に向き合っているピアノの先生方にも、ぜひ一度この視点を共有できたら嬉しいです。
その他教材、教具はこちらから一覧をご覧いただけます。