近年、子供のための教本はたくさん存在します。
実際に教室で使っている教本を年齢、レベル別にご紹介します。

Sakiピアノ教室主宰、飯沢紗希
- 音楽一家に生まれ、3歳からピアノ講師である母親にピアノを教わる
- 桐朋学園大学卒業後、ピアノ教室開講
- 我の強い子どもで、母親と猛烈な親子バトルを経験
自身の経験から、ピアノ練習における親子バトル、子どもの練習に悩む方へ、相談窓口を設けています。
2歳から年少さんまでで使用する教本
まず、2歳からのピアノでは、教本は使用していません。
ほとんどの教本が早くて3、4歳から。
無理やり教本を使用するのではなく、子どもの特性を考えたうえで、今できるレッスンを行っています。
Sakiピアノ教室では2歳から、感覚で使用できるたくさんの手作り教具をご紹介しています。
▶Sakiピアノ教室手作り教具、教材
それぞれダウンロード、ご購入もしていただけますのでご活用ください。
 さき先生
さき先生「教えない」レッスンでは、子どもが感覚で使える特製教具を使いながら、独自カリキュラムを使用し、教本へのアプローチをしています。
幼児レッスンカリキュラム構築コンサルも行っていますで、幼児レッスンにお悩みになる方、1度ご覧ください。
▶幼児レッスンカリキュラム構築コンサル
教本を導入するタイミング、実際にプレピアノレッスンカリキュラムが終わった後に使用している教本についてはこちらにまとめてあります。


どうしても…2歳から教本を使うには
2歳からのピアノレッスンでどうしても教本を使いたい場合はこちらがおすすめです。
ピアノを実際に触れてもらう時に使用する教本はこちらです。
こちらだけではなく一緒に発売されているカードも使います。
グーやパーでピアノを触りながら、お歌で楽しく音のお名前も覚えていきます。
この教本が終わるころには音の配列をド→シ、ド←シの順番が理解できています。
複数曲を何回も何回も繰り返して楽しく取り組んでもらっています。
2歳頃だとちょうどいやいや期も重なる子が多く、こだわりを持つころです。
子供が好きなお歌はずっと歌います。
聴く耳を育てる、感性を育てる教本
そして同時に耳を鍛えてもらいます。
先生が弾くピアノを聴き、どんなイメージを持つことが出来るか?
だれがやってきたかな?
ぞうさんかな?ねずみさんかな?うさぎさんかな?
曲の強弱や、テンポを聴き取る課題です。
リトミックレッスンでも良いのですが、教本を使って進めていきたい先生におすすめです。
すこしピアノの前に座れるようになってきたら
すこし長くピアノの前に座れるようになって来たらどんどん弾いていきます。
言わずもがな、有名なバスティン教本の導入書のようなものです。
左右の手の確認、指使いの確認、黒鍵のみで弾いていく曲などがカラフルな絵と共に描かれているため、3歳~未就学児の初めてのピアノレッスンにとても使いやすい教本です。
こちらの本も、まずは絵音符から。
「ぴあのだいすき」の続きとして使用できます。
まだ幼い子供にとって、何度も繰り返し学習できるので、無理なく進められます。
子供の食いつきが良いのはやはりゴーゴーピアノ。
これをメインで使用することはないですが、子供たちが楽しみながらド~ソの音符、4分音符、2分音符、4分休符を覚えることが出来ます。
また楽譜が簡易的なので、音符に色を塗ってもらったり、音符をきちんと完成させてもらったり、これ1冊で様々なことを勉強できます。
年少~未就学児
年少さんから未就学児の生徒の使用楽譜は様々です。
上記の教本をそのまま使用し進めることもありますが、生徒に応じて他の教本も使います。
~初級の生徒には
バスティンシリーズのベーシックのピアノ、テクニック、パフォーマンス、セオリーが1冊にまとまった教本です。
まだ未就学の生徒にはこちらを進めていくことが多くあります。
こちらのリズムの本はゴーゴーピアノの後に使用しています。
アプローチの仕方を工夫すればリズムへの理解が深まります。
年少さんからこちらを使用するのはやや難しい印象ですので、ゴーゴーピアノを3まで終わらせた生徒に使っています。
どんどん進めてくれます。
みんなのおけいこシリーズは昔からあるため、曲が少々古めですが、ミドルC(真ん中のド)から始まり、音符の説明もとても分かりやすいです。
この1はとても使いやすく使用しています。
これだけでは少し足らないので他の教本を組み合わせます。
こちらのオルガンピアノの本も昔からありますが、新版が出ています。
絵が柔らかくなり、子供たちも取り組みやすそうです。
ミドルCから始まりますが、早い段階で他のポジションの勉強も出来ます。
こちらも昔からあるテクニックの教本です。
1曲1曲がとても短く、たくさんの曲をテンポよく進めることが出来ます。
(本来は12曲を1度でお勉強するのですが、実際は3曲~4曲ずつ進めています)
しっかりと教える側が目的を汲んで取り組めば、さまざまなテクニックが身につく教本です。
初級~中級の生徒には
導入書が終わり、自分で音が読め、音楽をある程度感じることが出来るようになって来たら、ハノンやブルグミュラー、ツェルニー、プレインヴェンションなどに取り組んでいきます。
子供用の楽譜には挿絵があり、子供たちが曲のイメージを付けやすくなっています。
ハノンは生徒によって、子供用のハノンを渡すか、普通のハノンを渡すか変えています。
音符に苦手意識のある生徒は子供のハノンの方が取り組みやすそうです。
(すべて終わるころに通常ハノンへ切り替えます)
未就学児さんのよく弾ける生徒にはツェルニーはこちらの2冊をよく使用します。
プレインヴェンションは曲によっては難しいですが、早くからバロック音楽への親しみがもてます。
ポリフォニー音楽に苦手意識が生まれる前になるべく取り組みたい1冊です。
小学生以上
小学生以上で初めて習う生徒には
小学生になってから初めてピアノを習う生徒も多くいます。
そんな生徒にはバスティンのベーシックスシリーズを使用しています。
生徒によってはプリマーを飛ばし、1から使用します。
初級以上の生徒には
初級以上の生徒には先に紹介した、ハノン、ツェルニー30番、プレインヴェンションが修了したらバッハのインヴェンション、ブルグミュラー、ソナチネなどを使用していきます。
それとは別に、曲集も多く使用します。
など。
また生徒によってはハノンのみならず、ピシュナも取り入れてもらいます。
また、ソナチネ程度になったらさまざまな小品を取り入れてもらいます。
生徒1人1人に合った教本選びを
「絶対これしか使用しない」と言うわけではなく、今までも色んな教本を使ってきました。
ぴあのどりーむ、ぴあのひけるよ!ジュニア、トンプソンなども過去に使用しています。
今ご紹介したのはほんの1例で、この先たくさんの教本が出てくると変更する可能性もあります。
- 指導しやすいもの
- 生徒が理解しやすいもの
であれば、なんでも使います。
指導が目指す方向が間違えていなければ、現在出版されている教本のどれを使っても、必要なものは身につきます。
どの教本を使うかも大切ですが、どのように教本を使うかもまた大切な要素です。



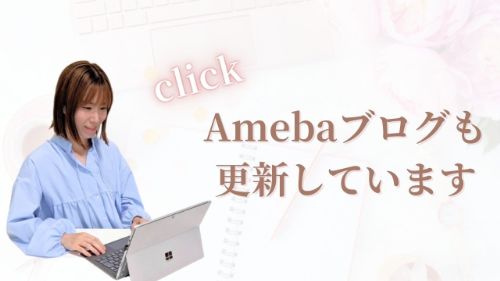

コメント
コメント一覧 (2件)
[…] ▶ピアノの先生が選ぶ年齢、レベル別教本 […]
[…] ピアノの先生が選ぶ年齢、レベル別教本 […]